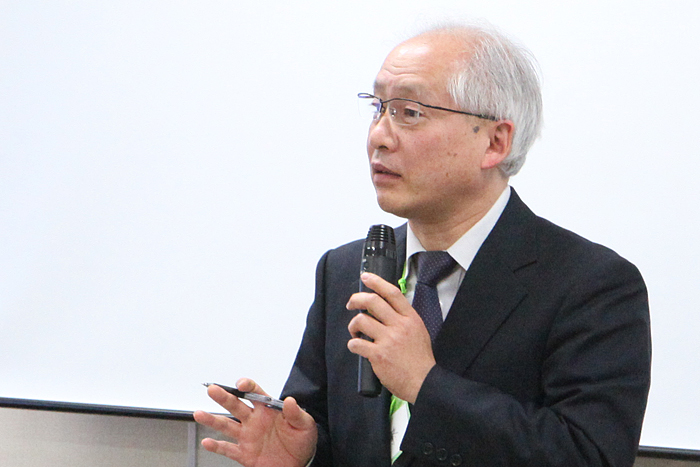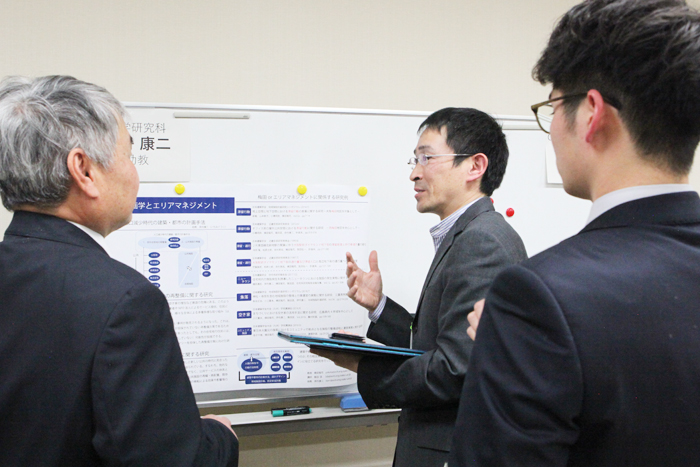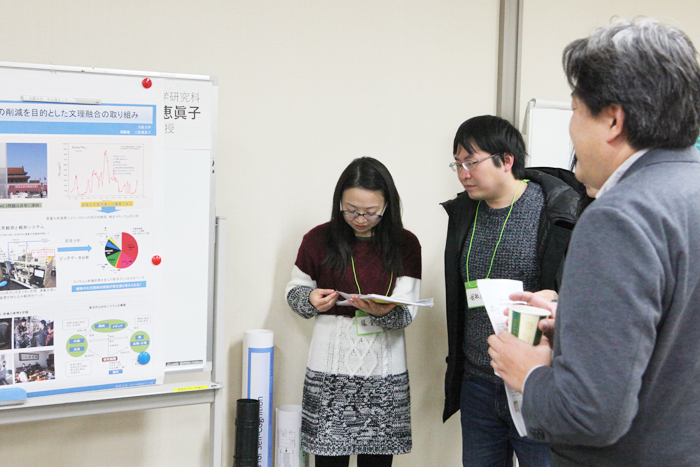大阪大学IBグラント大型産学共創コンソーシアム組成支援プログラムによる「梅田での大阪大学の取り組み報告会」開催報告〜大学を核とする共創まちづくりへ〜
2019.01.09(水)
梅田での共創まちづくりに期待する、50名以上が参集!
地域や人材の多様性をいかし、梅田発イノベーションの起爆剤になる!
まずは研究代表者の木多教授より、本プロジェクトへの2つの大きな期待が語られました。
「ひとつはエリアの多様性によるイノベーションへの期待。梅田には、民間企業では考えられない壮大なスケールで進められた阪急梅田駅周辺の都市開発や、永年にわたり困難を極めた権利関係の調整を信念で乗り越えた大阪駅前駅ビル再開発などにより、さまざまなエリアが成立してきました。個性豊かなこれらの地域の境界線を取り去って、まちの魅力や人材などが融合すれば、大きなイノベーションが起こる可能性があります。
もうひとつは人材の多様性によるイノベーションへの期待。本プロジェクトには、大阪大学からは人文社会学系から工学系まで多様な研究科の教員が参画し、企業や行政からも多様な分野や業界の方々に参加していただいております。このような方々によるアイデアの出し合いによって、新しいビジネス、土地活用、空間デザイン、さらには新しい公共サービスが生まれてくるようなイノベーションが起こる可能性がある。
我々のプロジェクトが、このようなイノベーションを起こす起爆剤になってくれればいいと考えています。」
大学がアンカーとなるまちづくりへ
次に、森栗先生より、これまでの大阪大学エリアマネジメント研究会の経過と今年度の取組みについての報告がありました。
「︎大学には多様なシーズがあり、まちには市民リソースや企業のシーズ、行政のファシリテーションがある。そういう中での対話のプラットフォームをつくることが重要だと考え、大阪大学エリアマネジメント研究会が始まりました。2年目はいよいよ梅田に出て行こうということで、木多先生のプロジェクトがIBグラントに採択いただけた。大学が核となる日本初の共創対話型まちづくりを、大阪大学が梅田で実験するのです。自動運転、ロボット宅配、都市農業、ゴミゼロ、ゼロエネルギーそれにオーガニックレストラン・・こんなことをみんなで議論をしていきたい。その過程で学生も社会人も育っていって欲しいと思います。そのはじまりが今日です。
人文社会系から工学系まで、阪大の幅広い研究者が参画
続いて、今回のプロジェクトに参画する大阪大学の教員たちから、自己紹介がありました、
① 工学研究科 地球総合工学専攻 建築・都市デザイン学講座 建築・都市計画論領域
教授 木多 道宏
私の研究室の留学生は10名を超え、学生は30人以上、ドクターコース8名という凄まじい環境です。私の専門はアーバンデザイン、まちづくり、コミュニティデザインです。未来のデザインや未来づくりをするためには、過去から普遍の原理を読み解いて地域文脈をつくり、それをもとに検討しています。私たちの研究室にかかったら、あらゆる地域の人生が解き明かされていきます。本プロジェクトでは、ロンドン大学とケンブリッジ大学へ調査にうかがう予定です。
ところで、阪大は地球規模課題に立ち向かうために、ロンドン大学とグローバル・パートナーシップを結び、そのキックオフワークショップが3月28日に開催されます。テーマの一つに「University and Society」があります。UCLは大学を核とした共創まちづくりに特別な実績がありますので、当研究会に大きなヒントが得られると思います。成果が得られましたら、改めてこの研究会にご報告できることを楽しみにしております。
② 文学研究科・文学部人文地理学教室
教授 堤 研二
文学部には人間が悩んだときに、重要なことを教えてくれる学問分野がたくさん揃っています。人文地理学とは、人間と場所や空間、環境との関係性を研究する学問。我々の研究室では、「国際ハブ空港ネットワークの分析」、「駅間の開発」、「JR新駅のインパクト」など、実践的な研究を行っています。私自身は、都市から農山村にわたる人口減少地域社会の持続可能性についての研究が専門です。現在は隠岐の島を対象とした研究を行っています。
梅田の開発については、ここを拠点として、西日本の核になるような地域空間づくりができればいいなと思っています。
③ 人間科学研究科 人間行動学講座
教授 三好 恵真子
私の研究室では、主に環境問題を研究しており、技術系はもちろん、社会学、政治学、経済学を含む、さまざまな専門知識を持った学生達が集まります。日々、さまざまな学問に触れながら対話をし、文理融合という世界をつくり上げています。私たちの方法論のポイントは、実践志向型、課題解決型の、地域研究。現場に入って、そこで起こっていることを全て、ありのまま受け止めて、何ができるか、当事者の視点でなにができるかを考えていくようにしています。多様な研究をすすめている人間科学研究科の学生が、こうしたプロジェクトで育ってくれたらと願います。
④ 工学研究科 建築・都市人間工学領域
助教 伊丹 康二
研究室の研究テーマは建築・都市文化。建物の中や外とか、まちの中といったところでの人の行動、群衆の行動などの対応関係や、どういった空間でどのような行動が起きてくるのか?そういったものを研究しています。私自身は、公共施設の再編や郊外住宅地の再生を研究しています。机上で考えるだけでなく、地元の住民の人たちと一緒に考えてこうとしています。梅田とどのように関われるかは、これから議論していきたいと思います。
⑤ COデザインセンター
特任教授 イステッキ・ジハンギル
私の専門分野は都市や建築物といった空間集合体が人間の行動・行為によって、どのように構成・デザインされるかというところ。私の具体的なミッションは、都市や公共の場の中でのそれらに関する研究・実践そして人材教育。
2010年以降、世界的に人口の50%が都市部に集中するようになり、空間的に限られた場で生活し、仕事をすることが、人々のライフスタイルとなっている。その結果、都市は多くの社会問題に直面している。例えば、都市集中化、高齢化、少子化、不平等、危機管理など。
都市や公共空間をデザインすることで、人間的社会的実践の場を、どのように共創できるのか?
大学は都市が直面する問題を解決するうえで、どのような役割を果たせるのか?
うめきたをモデルに、これからの日本社会にとって重要な疑問を解き明かしていきたいと思っています。
⑥ COデザイセンター
教授 松浦 博一
私はCOデザインセンターに属しており、URA(University Research Administrator)という立場。いろいろな形で周りの先生方のお役に立つ役割で、研究マネジメントを担っています。出身は三和銀行。メガバンクで30年、システム会社で10年、民間企業でいかに人と人を繋ぐかという仕事をしてきました。今回、この研究会に参画させていただいた私の役割は、今日ご参加いただいた民間企業の皆さま、自治体の皆さま、それと大学の先生方、全ての方々との会話を進めて、産官学の連携をスムーズに繋げることだと思っています。今まで培ってきたネットワークも生かしながら、皆さまとしっかりと会話して、梅田のまちづくりに貢献したいと思います。
⑦ 社学共創本部
特任助教 佐伯 康考
私の専門は多文化共創、具体的にいうと「移民」です。2019年は外国人政策の歴史的転換点と言われています。2025年の大阪万博も決まりましたので、インバウンドや増加する外国人とどう向き合っていくかということが、非常に重要なテーマになってくると思っています。
阪大の話としては、2年後の箕面新キャンパスへの移転があります。多くの外国人留学生や外国人研究者が、地域とどういう関係をつくっていくのか、とても重要なテーマになってくると思います。
⑧ COデザインセンター
特任助教 辻 寛
まちづくり、都市政策の研究で、イギリスのカーディフ大学で修士号を取得し、現在、人間科学研究科の博士後期課程で学んでいます。スポーツや交通を通じて、どのように地域の人々がまとまっていくか、繋がっていくか、そういった道具としてのスポーツや交通を研究テーマとしています。
この数年は、学生の方々とのコミュニケーションをとても大切にする講義を、森栗先生の元で学んできました。人々との違いや同一性を理解しながら一緒に学んでいく、コミュニケーション型の研究・教育に関わらせていただいている関係で、このプロジェクトに参加させていただいております。
地域とともにある、新たな大学の姿へ
入試改革で阪大が変わる
大学での伸びしろを測る入試が増える
文部科学省は、まず基本的な知識と技能を身につけて、その上に判断力、思考力、表現力をつけて、その後の高等教育(大学以上)では、主体性、対応性、協働性を身につけなさいと言ってきた。これを受けて、私は主体性、対応性、協働性を測るような、言い換えれば、大学入学後の伸びしろを測るような入試を実現するために、いろいろな大学のお手伝いをやってきました。例えば、四国の善通寺にある四国学院大学という小さな大学。ここでは、数名のグループごとにレゴで巨大な艦船をつくらせたり、本四架橋3本のうち2本を廃止する(あくまで架空の話です)ための議論をさせたりしました。全体設計、作業行程策定、役割分担、そして地道な手作業まで、多様な能力を評価する試験です。このような、大学に入ってからの伸びしろを測る試験は、先端的な小さな大学ほど実現しやすいのです。
何を学ぶかではなく、誰と学ぶか
一方、阪大も日本最高、世界最先端の入試をつくるために、リーディング大学院のリーディングプログラムの試験に取り組んできました。これを私は7年ほど担当させていただいたわけですが、2泊3日で40人の学生をホテルに缶詰めにして、演劇制作や意見広告制作をはじめ、様々な課題をこなしてもらったりしました。それで何を評価しようとしているかというと、右脳と左脳をシャッフルしながら、集団での活動と個人の活動を交互に入れながら、それでも論理的に話せるか、それでも人の意見に耳を傾けることができるかを見ているのです。
NASAやJAXAでの宇宙飛行士選抜は、命のやり取りをできる仲間を選んでいく試験です。だからいろいろな能力が必要とされる。共同体がピンチの時にジョークを言って和ますことができるか、斬新な発想でピンチを切り抜けられるか、だけど普段から地道な作業に加わっていないと信用されない。つまり、多様な人材が必要になってくるのです。日本の大学の入試もこういうスタイルに変わっていかざるを得ないと思っています。
インターネットの進歩で、知識や情報はいつでもどこでも入手できます。なので、大学では何を学ぶかではなくて、誰と学ぶかの方が重要なのです。学生の多様性を確保しないと、学びの場になりません。学生たちは仲間からより多くのことを学び、教員の言うことなんかあまり聞いてませんよ。大学の入試改革の一番の肝はここあります。残念ながら、ここが国民に伝わっていないのが現状です。